2010年02月09日
どこに目標を置くか
さて、前回の記事では“いい就職活動ができた”ってどういうことだろうかという話をしましたが、これにはもっと先を見据えた上での背景があります。
近い将来、おそらく日本でも、もっとたくさんの海外の方と仕事を一緒にする時期がくると思います。
皆さんが身近に感じているところで言えば、コンビニエンスストアで留学生がアルバイトをしてるなんてことは、もうよく見る光景になってきているんじゃないかと思います。もちろんこの延長線上には、日本の企業で正社員として海外の方が働いているという姿も、不思議じゃない時代になってくることが考えられます。早い企業では、規模の大小に関わらず、既にそうなっています。
昨今では企業側も、国内の需要がなかなか回復しないので、海外に向けて事業を展開していくことが増えてきましたから。
こういった背景を考えると、みなさん就職活動生のライバルは、国内の学生さんだけではなくなってきたと言えるのではないでしょうか。実際に就職活動でも、留学生と一緒に面接を受けたりする機会は増えてきているんではないでしょうか?
海外の大学生は、日本語の語学力に課題はあるにしても、企業に入って活躍するための要素といった点では、おそらくほとんどの日本の大学生よりも高いスキルを持っています。
自分が5年前にシンガポールに行った時は、そこで会った50人くらいの大学生の9割は、最低でも3ヶ国語を
しゃべれるという状態でした。すごい学生になると5ヶ国語です。休学して、アメリカでMBAをとってから
シンガポールの大学に戻ってきた女子学生にも会いました。自分もその時は大学生でしたが、現時点では全く彼らには敵わないと心底思ったのを覚えています。
そういった人達と今後は闘っていかなくてはならないと思うと、“内定をもらう”といった目標を立てて、それに1年間もの時間をかけている暇はないように思います。
“自分を価値のある人材にする”といったもっと先の目標を立て、それに対して時間を使っていくことが大切ではないかと。そう考えると、自分の今取り組んでいる、大学の専門的な研究やゼミでの活動に力を入れることの方が、遠回りのようで実は近道なのかもしれません。
近い将来、おそらく日本でも、もっとたくさんの海外の方と仕事を一緒にする時期がくると思います。
皆さんが身近に感じているところで言えば、コンビニエンスストアで留学生がアルバイトをしてるなんてことは、もうよく見る光景になってきているんじゃないかと思います。もちろんこの延長線上には、日本の企業で正社員として海外の方が働いているという姿も、不思議じゃない時代になってくることが考えられます。早い企業では、規模の大小に関わらず、既にそうなっています。
昨今では企業側も、国内の需要がなかなか回復しないので、海外に向けて事業を展開していくことが増えてきましたから。
こういった背景を考えると、みなさん就職活動生のライバルは、国内の学生さんだけではなくなってきたと言えるのではないでしょうか。実際に就職活動でも、留学生と一緒に面接を受けたりする機会は増えてきているんではないでしょうか?
海外の大学生は、日本語の語学力に課題はあるにしても、企業に入って活躍するための要素といった点では、おそらくほとんどの日本の大学生よりも高いスキルを持っています。
自分が5年前にシンガポールに行った時は、そこで会った50人くらいの大学生の9割は、最低でも3ヶ国語を
しゃべれるという状態でした。すごい学生になると5ヶ国語です。休学して、アメリカでMBAをとってから
シンガポールの大学に戻ってきた女子学生にも会いました。自分もその時は大学生でしたが、現時点では全く彼らには敵わないと心底思ったのを覚えています。
そういった人達と今後は闘っていかなくてはならないと思うと、“内定をもらう”といった目標を立てて、それに1年間もの時間をかけている暇はないように思います。
“自分を価値のある人材にする”といったもっと先の目標を立て、それに対して時間を使っていくことが大切ではないかと。そう考えると、自分の今取り組んでいる、大学の専門的な研究やゼミでの活動に力を入れることの方が、遠回りのようで実は近道なのかもしれません。
タグ :就職活動
2010年02月05日
じっくりと時間をかけて活動してほしい
今日、あるお客様先から、先月このブログでも紹介した当社のイベントに参加して、そこで出会った学生が説明会+適性検査を受けて“成績トップで通過した”とのお話をお聞きしました。
もちろんイベント自体には課題もたくさんありますが、こういった結果が出たことをご報告いただけるのは非常に有難いです。
ただ、本番はこれからで、そういった候補者が無事内定をもらって入社し、社内で活躍するまで育ってくれて初めて“いい採用”をしたという結果が得られると思います。
もちろんこれは、就職活動をしている学生の皆さんも同じで、内定をもらって入社して、そこで活躍できる人材になって初めて“いい就職活動ができた”とわかります。
1時間もせずに終わる適性検査や面接がうまくいったからといって“いい就職活動ができた”とは言い切れない。逆に、適性検査や面接がうまくいかずに落とされたとしても、“就職活動がうまくいかなかった”ということにもなりません。
“早く内定がほしい!”という気持ちもわかりますが、ぜひ、自分をごまかすことなく、誠実に選考に臨んでほしいと思います。その分時間がかかったとしても、結果としてはいい就職ができると思います。
もちろんイベント自体には課題もたくさんありますが、こういった結果が出たことをご報告いただけるのは非常に有難いです。
ただ、本番はこれからで、そういった候補者が無事内定をもらって入社し、社内で活躍するまで育ってくれて初めて“いい採用”をしたという結果が得られると思います。
もちろんこれは、就職活動をしている学生の皆さんも同じで、内定をもらって入社して、そこで活躍できる人材になって初めて“いい就職活動ができた”とわかります。
1時間もせずに終わる適性検査や面接がうまくいったからといって“いい就職活動ができた”とは言い切れない。逆に、適性検査や面接がうまくいかずに落とされたとしても、“就職活動がうまくいかなかった”ということにもなりません。
“早く内定がほしい!”という気持ちもわかりますが、ぜひ、自分をごまかすことなく、誠実に選考に臨んでほしいと思います。その分時間がかかったとしても、結果としてはいい就職ができると思います。
2010年02月01日
何をしたかではなく、何のためにそれをしたか
先日、カメラマンの木村大作さんの講演を聞く機会がありました。
もう70歳というのに、約100人を前にマイクを使わず地声で講演をされました。
話題の中心となったのは、映画人生50年の節目として初監督をした『劔岳 点の記』についてでした。
ご自身も講演の中でおっしゃったのですが、聞いている私たちも強く感じたのが、“映画をつくる”という仕事が、木村大作さんの生きることそのものであるということ。
また、映画を通して伝えたいメッセージが、木村大作さんが自身の生き方を通して世の中に伝えたいメッセージそのものであるということです。
映画をつくったことそれ自体、また、それがヒットしたことについて言うのではなく、その映画を通して木村大作さんがしたかったことを講演の中ではじっくりとお話いただきました。
まさに、今回の映画の核となる言葉にもある、
“何をしたかではなく、何のためにそれをしたかが大事です”
という言葉を体現している姿だと思いました。
これを聞き、改めて自分自身の仕事への姿勢を見つめなおしたいと思います。
もう70歳というのに、約100人を前にマイクを使わず地声で講演をされました。
話題の中心となったのは、映画人生50年の節目として初監督をした『劔岳 点の記』についてでした。
ご自身も講演の中でおっしゃったのですが、聞いている私たちも強く感じたのが、“映画をつくる”という仕事が、木村大作さんの生きることそのものであるということ。
また、映画を通して伝えたいメッセージが、木村大作さんが自身の生き方を通して世の中に伝えたいメッセージそのものであるということです。
映画をつくったことそれ自体、また、それがヒットしたことについて言うのではなく、その映画を通して木村大作さんがしたかったことを講演の中ではじっくりとお話いただきました。
まさに、今回の映画の核となる言葉にもある、
“何をしたかではなく、何のためにそれをしたかが大事です”
という言葉を体現している姿だと思いました。
これを聞き、改めて自分自身の仕事への姿勢を見つめなおしたいと思います。
Posted by KNブログ at
00:03
│Comments(0)
2010年01月25日
“働く動機”が必要な理由
前回は、先週開催したセミナー内容について、簡単にご紹介させていただきましたが、その続きといいましょうか、もう一つだけ、ご紹介したいお話がありますので、引き続き書かせてもらいます。
採用の支援をしていると、社員さんへのインタビューをすることがよくあるのですが、入社3年名以内で頑張って仕事をしている人には、ある共通点があります。
それは、前回の投稿記事にも書きましたが、一つは“入社動機”が明確であること。それともう一つは、入社後に仕事をする中で、その会社で働き続きける理由を明確にしていること。つまり、“働く動機”を明確にしていることです。
実はその背景も前回の投稿記事と似通ってくるのですが、終身雇用制が終わり、転職市場がこれだけ充実している昨今では、“どんなに大変な思いをしても一社に留まる”という感覚が薄れてくるのも無理はありません。
しかし、そんな時代でありながら大変な思いをして一生懸命働いている人というのは、とにかく自分を成長させたいと思っているか、成長して実現したい『その会社で働く意味』を持っているかといった方が多いのではないかと思います。
逆に、そういったものを持っている人というのは、仕事の中で大変な思いをしても、それを耐え抜き、一人前に成長していくのではないかと思います。
そこで、セミナーの内容でもう一つお伝えしたいことが、入社後の教育の機会で、この“入社動機”を改めて確認すること。あるいは、それが入社段階で明確になっていなかったとしても、働きながらそれを明確にしていく機会や方法を提供することが必要ではないかということです。
やはり、若手の頃は“現場(職場)”に勝る教育環境というのはありません。極端な話、その“現場(職場)”で起こる様々な事柄に対して、それを乗り越えていく動機さえあれば、3年ほど経った後、人によって若干前後はするものの、十分に仕事を一人前にできる力を身につけることができます。
採用の支援をしていると、社員さんへのインタビューをすることがよくあるのですが、入社3年名以内で頑張って仕事をしている人には、ある共通点があります。
それは、前回の投稿記事にも書きましたが、一つは“入社動機”が明確であること。それともう一つは、入社後に仕事をする中で、その会社で働き続きける理由を明確にしていること。つまり、“働く動機”を明確にしていることです。
実はその背景も前回の投稿記事と似通ってくるのですが、終身雇用制が終わり、転職市場がこれだけ充実している昨今では、“どんなに大変な思いをしても一社に留まる”という感覚が薄れてくるのも無理はありません。
しかし、そんな時代でありながら大変な思いをして一生懸命働いている人というのは、とにかく自分を成長させたいと思っているか、成長して実現したい『その会社で働く意味』を持っているかといった方が多いのではないかと思います。
逆に、そういったものを持っている人というのは、仕事の中で大変な思いをしても、それを耐え抜き、一人前に成長していくのではないかと思います。
そこで、セミナーの内容でもう一つお伝えしたいことが、入社後の教育の機会で、この“入社動機”を改めて確認すること。あるいは、それが入社段階で明確になっていなかったとしても、働きながらそれを明確にしていく機会や方法を提供することが必要ではないかということです。
やはり、若手の頃は“現場(職場)”に勝る教育環境というのはありません。極端な話、その“現場(職場)”で起こる様々な事柄に対して、それを乗り越えていく動機さえあれば、3年ほど経った後、人によって若干前後はするものの、十分に仕事を一人前にできる力を身につけることができます。
タグ :新入社員教育
2010年01月21日
働く動機
先日からこのブログでもご紹介していました、新入社員研修を考えるセミナーを昨日開催しました。
◆『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』
http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/
今回のセミナーでは、新入社員の“入社前”“入社直後”“入社して現場配属した後”といった時間軸に沿って、昨今の事例を交えた話題をご紹介しました。
入社前については、今月初めに実施した学生の就職活動イベント。この企画運営の中で学ぶプロジェクトベースドインターンシップについてご紹介しています。
ここが、当社がお伝えさせてもらっている“育成採用”の重要なポイントの一つでもあるのですが、これだけ人材の流動化が激しくなった昨今では、能力の高低に関わらず、新入社員も早期に転職する可能性は否めません。“新入社員の早期の転職”と表現しましたが、世間ではこれを“早期離職”の問題として取り上げています。ただ、終身雇用の時代が終わり、どんな大きな会社でも必ず安定しているとは言い切れない昨今では、新卒であっても、入社する側の明確な入社動機と採用側の明確な採用動機をマッチングする必要があると考えます。
しかしながら、働いた経験の無い学生が、入社する会社の理念や職務としっかりとリンクする入社動機を持つことは非常に難しい。だからこそ、学生の段階である一定期間の“良質な仕事の経験”を提供し、『働く動機』を持つ機会を与えなければならないと思います。
そして、社会の中で“良質な仕事の経験”を提供できるのが、企業であると思います。
◆『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』
http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/
今回のセミナーでは、新入社員の“入社前”“入社直後”“入社して現場配属した後”といった時間軸に沿って、昨今の事例を交えた話題をご紹介しました。
入社前については、今月初めに実施した学生の就職活動イベント。この企画運営の中で学ぶプロジェクトベースドインターンシップについてご紹介しています。
ここが、当社がお伝えさせてもらっている“育成採用”の重要なポイントの一つでもあるのですが、これだけ人材の流動化が激しくなった昨今では、能力の高低に関わらず、新入社員も早期に転職する可能性は否めません。“新入社員の早期の転職”と表現しましたが、世間ではこれを“早期離職”の問題として取り上げています。ただ、終身雇用の時代が終わり、どんな大きな会社でも必ず安定しているとは言い切れない昨今では、新卒であっても、入社する側の明確な入社動機と採用側の明確な採用動機をマッチングする必要があると考えます。
しかしながら、働いた経験の無い学生が、入社する会社の理念や職務としっかりとリンクする入社動機を持つことは非常に難しい。だからこそ、学生の段階である一定期間の“良質な仕事の経験”を提供し、『働く動機』を持つ機会を与えなければならないと思います。
そして、社会の中で“良質な仕事の経験”を提供できるのが、企業であると思います。
2010年01月12日
採用よりも教育
さて、前回紹介したセミナーを受けて、またしばらく新人教育について考えていきたいと思います。
何度もご紹介しているとは思いますが、弊社では、教育事業を軸に、新卒者の採用支援も行っています。
今年の傾向としては、皆さんもご承知の通り、景気の波を受け、企業側は厳選採用ということで窓口を絞ってきています。もちろん学生側は就職難という状況で、一昨年とは大きく変化してきています。
しかしながら、状況は変わっているにも関わらず、採用活動の方法や就職活動の方法には大きく変化はありません。人数を絞っているので、選考段階では厳しくなっているものの、選考に至るまでのプロセスは景気の良い時とほとんど同じです。つまり、選考参加希望者の母集団を作ってそこから振いにかけていき、内定を決めるというやり方です。
弊社は、この採用活動のやり方や考え方に課題を感じています。
なぜか。
それは、新卒採用の元々の目的を考えると、見えてきます。新卒採用の大きな目的の一つは、採用した新卒者が長期に渡って会社に利益を還元してくれることにあります。短期でいいなら、経験のある中途採用をした方が得策ですから。
といった本来の目的を見返すと、変えていかなけければならない新卒採用の考え方に2つのポイントが出てきます。
一つ目は、会社に対して長期に渡って利益を還元してくれる人材であるかどうかが、採用選考の基準になっているのか。
採用選考時に非常にいい人材だと思っていた子が、3年もしない内に辞める、伸び悩んんで結果が出せないでいる、一方で期待もしていなかった人材がすごい活躍を見せている。こいった採用選考での評価と、入社後の実績がずれることはよくあることです。
だからこそ、今一度確認すべきは、採用選考の基準が、入社後長期に渡って貢献してくれる人材であるかどうかを見極めるものになっているかということ。そういった視点で、選考基準が厳しくなっているかどうかということです。
二つ目は、入社後に伸びる人材とそうでない人材の違いは何かを明確にすること。
改めて確認しますが、新卒採用で重要なのは、“入社後に長期に渡って活躍してくれるかどうか”です。極端な話をすれば、採用する人材がどんな人材であっても、新卒社員が入社後に長期に渡って活躍してくれるための教育方法や仕組みがあれば、採用は減らさなくてもいいんです。
であれば、どうやってよりよい人材に会えるかを模索するのと同じくらい、この“入社後に長期に渡って活躍してくれるためにどうするのか”を考えることは重要です。
そういった意味で、“入社後に伸びる人材とそうでない人材の違いは何かを明確にすること”というのが重要になってくると思います。
何度もご紹介しているとは思いますが、弊社では、教育事業を軸に、新卒者の採用支援も行っています。
今年の傾向としては、皆さんもご承知の通り、景気の波を受け、企業側は厳選採用ということで窓口を絞ってきています。もちろん学生側は就職難という状況で、一昨年とは大きく変化してきています。
しかしながら、状況は変わっているにも関わらず、採用活動の方法や就職活動の方法には大きく変化はありません。人数を絞っているので、選考段階では厳しくなっているものの、選考に至るまでのプロセスは景気の良い時とほとんど同じです。つまり、選考参加希望者の母集団を作ってそこから振いにかけていき、内定を決めるというやり方です。
弊社は、この採用活動のやり方や考え方に課題を感じています。
なぜか。
それは、新卒採用の元々の目的を考えると、見えてきます。新卒採用の大きな目的の一つは、採用した新卒者が長期に渡って会社に利益を還元してくれることにあります。短期でいいなら、経験のある中途採用をした方が得策ですから。
といった本来の目的を見返すと、変えていかなけければならない新卒採用の考え方に2つのポイントが出てきます。
一つ目は、会社に対して長期に渡って利益を還元してくれる人材であるかどうかが、採用選考の基準になっているのか。
採用選考時に非常にいい人材だと思っていた子が、3年もしない内に辞める、伸び悩んんで結果が出せないでいる、一方で期待もしていなかった人材がすごい活躍を見せている。こいった採用選考での評価と、入社後の実績がずれることはよくあることです。
だからこそ、今一度確認すべきは、採用選考の基準が、入社後長期に渡って貢献してくれる人材であるかどうかを見極めるものになっているかということ。そういった視点で、選考基準が厳しくなっているかどうかということです。
二つ目は、入社後に伸びる人材とそうでない人材の違いは何かを明確にすること。
改めて確認しますが、新卒採用で重要なのは、“入社後に長期に渡って活躍してくれるかどうか”です。極端な話をすれば、採用する人材がどんな人材であっても、新卒社員が入社後に長期に渡って活躍してくれるための教育方法や仕組みがあれば、採用は減らさなくてもいいんです。
であれば、どうやってよりよい人材に会えるかを模索するのと同じくらい、この“入社後に長期に渡って活躍してくれるためにどうするのか”を考えることは重要です。
そういった意味で、“入社後に伸びる人材とそうでない人材の違いは何かを明確にすること”というのが重要になってくると思います。
2010年01月07日
新入社員研修セミナー ~両者の変化への対応~
前回のブログでも紹介しましたが、今月1月20日(水)に新入社員教育についての人事担当者様向けセミナーを実施します。
…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…
◆2010年卒 新入社員研修セミナー◆
『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』
日時:1月20日(水)13:00~15:30
定員:30名
対象:企業の人事・人材開発・教育・研修のご担当者様
場所:ibb fukuokaビル 6階会議室 (福岡市中央区天神2-3-36)
[13:00~14:00]
【第一部】新入社員を自律型人材に育てる3つの要素
2010年新入社員の背景
2009年度新人研修の振り返りから見えてきた対策
プロジェクトベースドインターンシップから見る、新入社員育成のポイント
新入社員を受け入れる現場の準備
[14:05~15:20]
【第二部】職場の学びを進化・改善させる「WPL」
WPL開発の背景
WPL診断の活用法
職場育成力向上
業績との相関性を見る
活用事例
DLL開発の背景と狙い
※お申込みの方は下記URLからどうぞ。
http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/
…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…
教育の業界では、毎年必ず一定期間話題になる、この“新入社員教育”についてのセミナー。
もちろん、そう毎年毎年新しいプログラムを組み込むべきだ!なんてことを言うわけではありませんが、やはり、ここ数年大きく経済環境が変動している状況に合わせて、新入社員の受入れ方法も少しずつ変えていく必要があると思います。
世間一般では“ゆとり世代”という、どちらかというと新入社員側にばかり問題があるような記事などが出回っていますが、自分が思うに、戦後の日本は毎年『豊かに』なってきたわけですから、20年前に新入社員として会社に入った方も、その当時会社を支えている30代、40代の社員さんから見れば『ゆとり世代』だったことは間違いないんじゃないかと思います。
また、20年前には話題にも上らなかった“新入社員”という括りが、昨今ではよく話題に上るのも、ほとんどの会社が終身雇用が前提だった時代と、人材の流動化が激しくなった昨今の背景を比べれば、注目度が変わるのも当然だと思います。何しろ会社に残り続ける人が少なくなったわけですから、真っ白な状態から会社の理念や業務を受け継いでいく新入社員に、以前よりも大きな期待がかかってくるのも当然のことだと思います。そして、期待がかかるからその“ギャップ”が見えた時に指摘される。これも当然の結果だと。
よって、上記したようなことを踏まえると、もちろん毎年入ってくる新入社員は年々少しずつ変化しており、その変化は“良い変化”も“悪い変化”も含んでいます。同様に、企業側も毎年変化しており、その変化は“組織の人材育成機能”といった点で“良い変化”も“悪い変化”もしているということです。
では、この両者の“良い変化”をどのように活かし、“悪い変化”に対してどのように対応していくかといったことが、今回のセミナーの主題となります。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください!
…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…
◆2010年卒 新入社員研修セミナー◆
『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』
日時:1月20日(水)13:00~15:30
定員:30名
対象:企業の人事・人材開発・教育・研修のご担当者様
場所:ibb fukuokaビル 6階会議室 (福岡市中央区天神2-3-36)
[13:00~14:00]
【第一部】新入社員を自律型人材に育てる3つの要素
2010年新入社員の背景
2009年度新人研修の振り返りから見えてきた対策
プロジェクトベースドインターンシップから見る、新入社員育成のポイント
新入社員を受け入れる現場の準備
[14:05~15:20]
【第二部】職場の学びを進化・改善させる「WPL」
WPL開発の背景
WPL診断の活用法
職場育成力向上
業績との相関性を見る
活用事例
DLL開発の背景と狙い
※お申込みの方は下記URLからどうぞ。
http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/
…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…
教育の業界では、毎年必ず一定期間話題になる、この“新入社員教育”についてのセミナー。
もちろん、そう毎年毎年新しいプログラムを組み込むべきだ!なんてことを言うわけではありませんが、やはり、ここ数年大きく経済環境が変動している状況に合わせて、新入社員の受入れ方法も少しずつ変えていく必要があると思います。
世間一般では“ゆとり世代”という、どちらかというと新入社員側にばかり問題があるような記事などが出回っていますが、自分が思うに、戦後の日本は毎年『豊かに』なってきたわけですから、20年前に新入社員として会社に入った方も、その当時会社を支えている30代、40代の社員さんから見れば『ゆとり世代』だったことは間違いないんじゃないかと思います。
また、20年前には話題にも上らなかった“新入社員”という括りが、昨今ではよく話題に上るのも、ほとんどの会社が終身雇用が前提だった時代と、人材の流動化が激しくなった昨今の背景を比べれば、注目度が変わるのも当然だと思います。何しろ会社に残り続ける人が少なくなったわけですから、真っ白な状態から会社の理念や業務を受け継いでいく新入社員に、以前よりも大きな期待がかかってくるのも当然のことだと思います。そして、期待がかかるからその“ギャップ”が見えた時に指摘される。これも当然の結果だと。
よって、上記したようなことを踏まえると、もちろん毎年入ってくる新入社員は年々少しずつ変化しており、その変化は“良い変化”も“悪い変化”も含んでいます。同様に、企業側も毎年変化しており、その変化は“組織の人材育成機能”といった点で“良い変化”も“悪い変化”もしているということです。
では、この両者の“良い変化”をどのように活かし、“悪い変化”に対してどのように対応していくかといったことが、今回のセミナーの主題となります。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください!
2010年01月04日
景気が上向かない、だからこそ・・・
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
さて、年が明けて新卒採用、就職活動も本格化します。
当社でも年明け早々ですが、明日は合同説明会を開催します。↓

学生と企業がじっくりと向き合い話し込むこのイベントは、業界研究や企業理解を深めるのに役立ったという声もそうですが、それ以上に“自分自身の成長の機会となった”という声が上がります。内定をゴールとしない、もっと先を見据えた就職活動、採用活動を目指す“育成採用”の象徴的な企画の一つです。
また、今月20日(水)には、これから入ってくる新入社員の育成方法についてのセミナーを人事担当者様を対象に実施します。上記のように、普段から多くの学生と一緒に活動をしている当社ならではのデータを元に、これから入社してくる新入社員の育成方法について考えていきます。
なかなか上向かない昨今の経済環境下では、新たに大きな投資をするのではなく、既に社内にある資源を活用していくことで売上を確保していくしかありません。そしてその“既に社内にある資源”の中で最も大きな可能性を持ち、重要な役割を持っているがヒトという資源であると当社は考えます。
今年も“人財”というキーワードを軸に、このブログでいろいろとご紹介していこうと思います。
さて、年が明けて新卒採用、就職活動も本格化します。
当社でも年明け早々ですが、明日は合同説明会を開催します。↓

学生と企業がじっくりと向き合い話し込むこのイベントは、業界研究や企業理解を深めるのに役立ったという声もそうですが、それ以上に“自分自身の成長の機会となった”という声が上がります。内定をゴールとしない、もっと先を見据えた就職活動、採用活動を目指す“育成採用”の象徴的な企画の一つです。
また、今月20日(水)には、これから入ってくる新入社員の育成方法についてのセミナーを人事担当者様を対象に実施します。上記のように、普段から多くの学生と一緒に活動をしている当社ならではのデータを元に、これから入社してくる新入社員の育成方法について考えていきます。
なかなか上向かない昨今の経済環境下では、新たに大きな投資をするのではなく、既に社内にある資源を活用していくことで売上を確保していくしかありません。そしてその“既に社内にある資源”の中で最も大きな可能性を持ち、重要な役割を持っているがヒトという資源であると当社は考えます。
今年も“人財”というキーワードを軸に、このブログでいろいろとご紹介していこうと思います。
2009年12月10日
学ぶ理由
昨日は当社の採用イベント『BizPASSトップゼミ』が開催されました。
↓
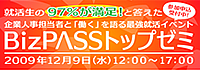
最終の参加者数は500人強となり、お陰様で非常に盛り上がりました。
イベント運営も今年は新メンバーで初めての開催でしたが、非常にスムーズに行ったように思います。
もちろん改善点はたくさん上がりましたが。
そして、今年もやはり、イベント企画・運営に携わった学生は、会場でも非常に際立っていました。
後援をいただいた公的機関の方からも、“スタッフの学生の気遣いは社会人にも引けを取らないですね”と
いった有難いコメントをもらっています。
イベントの成功という目標に向かって、必要に駆られて知識やスキルを身につけていく。
この、“学ぶ理由”があるのとないのとでは大きな違いが出ることを毎年のように実感させられます。
↓
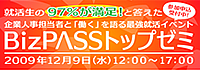
最終の参加者数は500人強となり、お陰様で非常に盛り上がりました。
イベント運営も今年は新メンバーで初めての開催でしたが、非常にスムーズに行ったように思います。
もちろん改善点はたくさん上がりましたが。
そして、今年もやはり、イベント企画・運営に携わった学生は、会場でも非常に際立っていました。
後援をいただいた公的機関の方からも、“スタッフの学生の気遣いは社会人にも引けを取らないですね”と
いった有難いコメントをもらっています。
イベントの成功という目標に向かって、必要に駆られて知識やスキルを身につけていく。
この、“学ぶ理由”があるのとないのとでは大きな違いが出ることを毎年のように実感させられます。
タグ :育成採用
2009年12月02日
日々の機会をどれくらい活かせているか
少し間が空きましたが、再び現場での学習要素について考えいきたいと思います。
前回の、現場での学習要素についての話(学びの共同体)では、“活動をするという主体的な学びの場”になるということをご紹介しました。
この前回の話をさらに噛み砕いて捉えていったのが、今回ご紹介する話です。
皆さんは、“これまで一度も仕事で失敗をしたことがない”と言い切れる方はいらっしゃるでしょうか。
おそらくほとんどの方はNOだと思います。もちろん私もNOです。むしろ、同年代では数が多い方にあたるという自信があります。
当然ですが、仕事というのは人間が作ったものですので、後発的に作られています。よって、何かの仕事を最初から全てできるという人が生まれてくるという事はありません。人は生まれてから、その後に仕事というものに触れていくので、大小の差はあるにせよ、当然何かしらの失敗を経験します。
そして、仕事における失敗はやりっぱなしでは終わりません。それを解決して初めて仕事というのが成り立つことになるので、失敗をすれば、その後は何かしらの解決策を講じています。
この、仕事という活動の中で、人は必ず問題を抱え、それを解決していくということ。言い換えるなら、自分のこれまでの経験でできるやり方でやってみて、失敗し、そのやり方ではない違うアプローチを生み出し、問題を解決していく。この一連のプロセスで人は学んでいるということを提唱したのが、フィンランドの教育学者のエンゲストロームです。
エンゲストロームはこの学習を「創造的学習」と呼んでいます。
仕事は不確定要素が高く、また、日々少しずつ変化しているという意味ではどんな人でも絶対はありません。定義にもよりますが、あのイチローでさえ、3回に2回は失敗をしているんです。その失敗の中で、“次はこうしてみよう”という創造をし、学んでいます。
毎日訪れている学習の機会をどれくらい活かせているか。その質によって大きな格差が生まれてきます。
前回の、現場での学習要素についての話(学びの共同体)では、“活動をするという主体的な学びの場”になるということをご紹介しました。
この前回の話をさらに噛み砕いて捉えていったのが、今回ご紹介する話です。
皆さんは、“これまで一度も仕事で失敗をしたことがない”と言い切れる方はいらっしゃるでしょうか。
おそらくほとんどの方はNOだと思います。もちろん私もNOです。むしろ、同年代では数が多い方にあたるという自信があります。
当然ですが、仕事というのは人間が作ったものですので、後発的に作られています。よって、何かの仕事を最初から全てできるという人が生まれてくるという事はありません。人は生まれてから、その後に仕事というものに触れていくので、大小の差はあるにせよ、当然何かしらの失敗を経験します。
そして、仕事における失敗はやりっぱなしでは終わりません。それを解決して初めて仕事というのが成り立つことになるので、失敗をすれば、その後は何かしらの解決策を講じています。
この、仕事という活動の中で、人は必ず問題を抱え、それを解決していくということ。言い換えるなら、自分のこれまでの経験でできるやり方でやってみて、失敗し、そのやり方ではない違うアプローチを生み出し、問題を解決していく。この一連のプロセスで人は学んでいるということを提唱したのが、フィンランドの教育学者のエンゲストロームです。
エンゲストロームはこの学習を「創造的学習」と呼んでいます。
仕事は不確定要素が高く、また、日々少しずつ変化しているという意味ではどんな人でも絶対はありません。定義にもよりますが、あのイチローでさえ、3回に2回は失敗をしているんです。その失敗の中で、“次はこうしてみよう”という創造をし、学んでいます。
毎日訪れている学習の機会をどれくらい活かせているか。その質によって大きな格差が生まれてきます。
2009年12月01日
強い意思で自分の甘さに勝つ
もう福岡も随分と寒くなりました。
相変わらず寒い時期の朝は、自分との葛藤です。
寒い冬の季節に、とても暖かい布団の中から飛び出すのには、朝起きた時から非常に強い意志がいるように思います。自分に甘くしようと思うと、簡単に二度寝、三度寝してしまいます。
逆に、強い意志で動き出すことができれば、非常に気持ちのいい朝を過ごせます。
そういった意味では冬の朝は、自分の意思がどれくらい強くなっているかを判断する指標になるように思います。
相変わらず寒い時期の朝は、自分との葛藤です。
寒い冬の季節に、とても暖かい布団の中から飛び出すのには、朝起きた時から非常に強い意志がいるように思います。自分に甘くしようと思うと、簡単に二度寝、三度寝してしまいます。
逆に、強い意志で動き出すことができれば、非常に気持ちのいい朝を過ごせます。
そういった意味では冬の朝は、自分の意思がどれくらい強くなっているかを判断する指標になるように思います。
2009年11月30日
できるかできないかではなく、やるかやらないか
ブログの更新に随分と日が空いてしまいましたので、先日までご紹介していた教育についての記事の前に、今日は少し違った話題を。
先週末に読んでいたビジネス誌に、こんな記事がありました。
ある組織のロボット開発のプロジェクトで、専門家に任せる前に、賞金を準備してアマチュアに公募してアイディアと実物を募りました。時間とお金をかけたのですが、意図したレベルのロボット開発は出てきませんでした。
ただ、そこで出てきた10数個の失敗例を基に専門家に任せたところ、短期間でハイクオリティの開発結果を出すことができたそうです。
実はこの、前段の『アマチュアに公募する』という企画は、この組織の“意図した失敗”であったと言います。つまり、失敗を前提で企画を実施し、そこから出てきた失敗例を基に本開発の設計の絞り込を行ったということです。
実は最近ではこういった“意図した失敗”を戦略的に行う企業もあるそうです。
もちろん企業であれば費用対効果が見合うかという計算はしっかりと行わないといけません。
ただ、個人に置き換えて考えるならば、これはもっと積極的に行ってもいいものではないかと思います。
自分自身もまだまだ力量の足りない時に様々な行動をし、たくさんの失敗を経験しましたが、その時の経験は今でも非常に重要な土台になっている気がします。
なぜなら、その失敗の経験の中にはたくさんの成功の要素と失敗の要因が含まれているからです。それをしっかりと見直しておけば、自然と成功確率もあがってきます。
ただ、ここで混同してはいけないのは、“意図した失敗”といっても、成功のためのプロセスと考えた上でのものです。あるいは、何かの目的に向かって進むための“経験”として考えた上で、結果的に失敗したということであるべきだと思います。
しかしながら、その“成功のプロセス”として“目的のため”ということすらわからないなら、とにかくやってみることをおススメしたいと思います。できるかできないかではなく、やるかやらないか。それだけだと思います。
先週末に読んでいたビジネス誌に、こんな記事がありました。
ある組織のロボット開発のプロジェクトで、専門家に任せる前に、賞金を準備してアマチュアに公募してアイディアと実物を募りました。時間とお金をかけたのですが、意図したレベルのロボット開発は出てきませんでした。
ただ、そこで出てきた10数個の失敗例を基に専門家に任せたところ、短期間でハイクオリティの開発結果を出すことができたそうです。
実はこの、前段の『アマチュアに公募する』という企画は、この組織の“意図した失敗”であったと言います。つまり、失敗を前提で企画を実施し、そこから出てきた失敗例を基に本開発の設計の絞り込を行ったということです。
実は最近ではこういった“意図した失敗”を戦略的に行う企業もあるそうです。
もちろん企業であれば費用対効果が見合うかという計算はしっかりと行わないといけません。
ただ、個人に置き換えて考えるならば、これはもっと積極的に行ってもいいものではないかと思います。
自分自身もまだまだ力量の足りない時に様々な行動をし、たくさんの失敗を経験しましたが、その時の経験は今でも非常に重要な土台になっている気がします。
なぜなら、その失敗の経験の中にはたくさんの成功の要素と失敗の要因が含まれているからです。それをしっかりと見直しておけば、自然と成功確率もあがってきます。
ただ、ここで混同してはいけないのは、“意図した失敗”といっても、成功のためのプロセスと考えた上でのものです。あるいは、何かの目的に向かって進むための“経験”として考えた上で、結果的に失敗したということであるべきだと思います。
しかしながら、その“成功のプロセス”として“目的のため”ということすらわからないなら、とにかくやってみることをおススメしたいと思います。できるかできないかではなく、やるかやらないか。それだけだと思います。
2009年11月20日
学びの共同体
今日もあるお客様先で研修のご提案をしてきたのですが、内容にはしっかりと共感いただいたように思います。
最近では、提案の際に自分が発する言葉、こちらからの質問や会話の中からお客様が発する言葉で、キーワードになるものを決めておき、その決めたキーワードが伝わったか、また、決めたキーワードをお客様から引き出すことができたかなどで、だいたいの商談確率が読めるようになってきました。
もちろんあくまで予測ですので、100発100中というわけにはいきませんが、随分読みの精度は上がってきたように思います。
こうやって、言葉の端々に気を使うのは、やはり当社が形の無いものを提供しているからという背景があります。お客様への伝わり方によって、商材に対して感じる価値が大きく変わってくるからです。
では、こういった対話の力を自分はどこで高めているかというと、もちろんお客様先もそうですが、一番は職場ということになります。
まず、当社の職場が他社の職場よりもたくさんの場所を使って置いているもの。これは書籍です。専門誌から一般誌まで様々な種類が置かれており、この書籍を普段から読みあさることで対話の元となる知識を身につけています。
それから、職場での会話も教育、採用、コンサルといったものが話題の中心となり、この会話の中で新しい知識を身につけたり、表現方法を学んだりします。
これが、今回ご紹介したい、職場が学習の場であるという一つの考え方です。
上記のように、職場という共同体に参加し、最初は簡単な役割から担い、次第に全体を理解する。そして、最終的には共同体の中心メンバーとなっていく。
このように、共同体への参加をしながら学習し、一人前のメンバーとなっていくような参加の仕方を、人類学者のレイブは『正統的周辺参加』という概念で表現しています。
これは、学校のような座学形式の学びの場では、学習者が“生徒”という受け身の立ち位置で学んでいくのに対して、共同体の“一メンバー”という立ち位置で主体的に学ぶ方法として非常に重要な学習の要素だと捉えたものです。
1990年代末から日本企業が注目した『ナレッジマネジメント』なんかは、まさにこの職場を学びの場としていく手法の一つになります。
最近では、提案の際に自分が発する言葉、こちらからの質問や会話の中からお客様が発する言葉で、キーワードになるものを決めておき、その決めたキーワードが伝わったか、また、決めたキーワードをお客様から引き出すことができたかなどで、だいたいの商談確率が読めるようになってきました。
もちろんあくまで予測ですので、100発100中というわけにはいきませんが、随分読みの精度は上がってきたように思います。
こうやって、言葉の端々に気を使うのは、やはり当社が形の無いものを提供しているからという背景があります。お客様への伝わり方によって、商材に対して感じる価値が大きく変わってくるからです。
では、こういった対話の力を自分はどこで高めているかというと、もちろんお客様先もそうですが、一番は職場ということになります。
まず、当社の職場が他社の職場よりもたくさんの場所を使って置いているもの。これは書籍です。専門誌から一般誌まで様々な種類が置かれており、この書籍を普段から読みあさることで対話の元となる知識を身につけています。
それから、職場での会話も教育、採用、コンサルといったものが話題の中心となり、この会話の中で新しい知識を身につけたり、表現方法を学んだりします。
これが、今回ご紹介したい、職場が学習の場であるという一つの考え方です。
上記のように、職場という共同体に参加し、最初は簡単な役割から担い、次第に全体を理解する。そして、最終的には共同体の中心メンバーとなっていく。
このように、共同体への参加をしながら学習し、一人前のメンバーとなっていくような参加の仕方を、人類学者のレイブは『正統的周辺参加』という概念で表現しています。
これは、学校のような座学形式の学びの場では、学習者が“生徒”という受け身の立ち位置で学んでいくのに対して、共同体の“一メンバー”という立ち位置で主体的に学ぶ方法として非常に重要な学習の要素だと捉えたものです。
1990年代末から日本企業が注目した『ナレッジマネジメント』なんかは、まさにこの職場を学びの場としていく手法の一つになります。
2009年11月19日
“見習う”とはよく言ったもの
今日は、弊社の支援しているNPO団体の学生スタッフと一緒に営業に行きました。
このスタッフは、もう随分と企業を回ってるだけあってお客様との対話もかなりスムーズに展開できます。
もちろん足りない部分もたくさんありますが、今日の訪問も、要所要所をサポートしただけでしっかりと話をまとめてしまいました。
こうやって学生と一緒に営業に行くと、自分自身の事を振り返るいいきっかけになります。
思えば、自分も営業を始めてから随分とやり方を変えてきたように思います。
最近でこそやっと自分自身の営業を自分自身で改善していけるようになったのですが、それまでは、同行させてもらう先輩の営業活動の方法を見よう見まねでやるしかありませんでした。
だから、時期によって随分やり方が違っています。
実はこれが、今日ご紹介したかった職場の学習要素の一つにあたります。
■認知的徒弟制
簡単に言うと、①上司(熟達者)が模範を示し、それを真似る。②上司(熟達者)が手取り足取り教える。③部下に一人でやらせてできないところをフォローする。④部下を独り立ちさせ、上司(熟達者)は手を引いていく。という4ステップから構成されている考え方です。
“OJTをやっている”というのが正にこれにあたるのですが、自身の経験を振り返ると、重要なのはこの4つの要素を時期をみて順序どおりにステップを踏んでいくことだと思います。
よく見るのが、上記の4つのステップのどれか一つだけをやっているケース。もちろん上記のように綺麗に切り分けることはできませんが、“自分の教育スタイル”ということで上記の4つどこかに偏っている方を見ることは少なくありません。
逆に、部下育成のうまい方に話を聞き、それをブレイクダウンしていくと、上記の4つのステップをうまく組み込んでいる事がよくあります。
“成長のステップをサポートする機能”これも職場の持つ教育要素の一つです。
このスタッフは、もう随分と企業を回ってるだけあってお客様との対話もかなりスムーズに展開できます。
もちろん足りない部分もたくさんありますが、今日の訪問も、要所要所をサポートしただけでしっかりと話をまとめてしまいました。
こうやって学生と一緒に営業に行くと、自分自身の事を振り返るいいきっかけになります。
思えば、自分も営業を始めてから随分とやり方を変えてきたように思います。
最近でこそやっと自分自身の営業を自分自身で改善していけるようになったのですが、それまでは、同行させてもらう先輩の営業活動の方法を見よう見まねでやるしかありませんでした。
だから、時期によって随分やり方が違っています。
実はこれが、今日ご紹介したかった職場の学習要素の一つにあたります。
■認知的徒弟制
簡単に言うと、①上司(熟達者)が模範を示し、それを真似る。②上司(熟達者)が手取り足取り教える。③部下に一人でやらせてできないところをフォローする。④部下を独り立ちさせ、上司(熟達者)は手を引いていく。という4ステップから構成されている考え方です。
“OJTをやっている”というのが正にこれにあたるのですが、自身の経験を振り返ると、重要なのはこの4つの要素を時期をみて順序どおりにステップを踏んでいくことだと思います。
よく見るのが、上記の4つのステップのどれか一つだけをやっているケース。もちろん上記のように綺麗に切り分けることはできませんが、“自分の教育スタイル”ということで上記の4つどこかに偏っている方を見ることは少なくありません。
逆に、部下育成のうまい方に話を聞き、それをブレイクダウンしていくと、上記の4つのステップをうまく組み込んでいる事がよくあります。
“成長のステップをサポートする機能”これも職場の持つ教育要素の一つです。
タグ :OJT
2009年11月18日
次の成長領域を知る
さて、前回に引き続き、現場での学び診断について考えていきたいのですが、その前に前提として、現場にはどういった学習の機会があるかをご紹介していきたいと思います。
実は、大きく分けても5つくらいの理論がベースにあるので、一つずつご紹介していきます。
一つ目は、『最近接発達領域』という考え方。
これは、すごく短くまとめるなら、“現在自身の独力で達成できるレベルと、人にサポートしてもらいながら達成できるレベルの差。”のことを言います。
実は人は、今現在自分自身では達成できないものを、人のサポートを得て達成することで、その差分を学ぶ
ことができます。
こういった、自分をサポートしてくれる環境があるのが、職場の持つ学習要素の一つです。
実は、大きく分けても5つくらいの理論がベースにあるので、一つずつご紹介していきます。
一つ目は、『最近接発達領域』という考え方。
これは、すごく短くまとめるなら、“現在自身の独力で達成できるレベルと、人にサポートしてもらいながら達成できるレベルの差。”のことを言います。
実は人は、今現在自分自身では達成できないものを、人のサポートを得て達成することで、その差分を学ぶ
ことができます。
こういった、自分をサポートしてくれる環境があるのが、職場の持つ学習要素の一つです。
2009年11月17日
職場の学習環境レベル
先週は学習効果を高める上でのルールというものの重要性について考えてみました。これに対し、今週は、このルールも含めた職場の環境が学習に及ぼす影響というものについて考えていきたいと思います。
実はここ最近、当社からも最も積極的にご紹介させてもらっているのが、“学習効果を高めるための職場環境改善のきっかけ”を作るツールです。
WPL診断
これは簡単に言うと、職場の学習環境レベルがどれくらいあるかを診断するツールです。
環境といっても、物理的なものだけでなく、人間関係やルールといった目に見えないものも含まれます。
そして、こういったものの現状を診断し、様々な切り口から職場の学習環境レベルを向上していくということが目的となります。
次回からは、この診断の裏付けとなる理論や事例などについてご紹介していこうと思います。
実はここ最近、当社からも最も積極的にご紹介させてもらっているのが、“学習効果を高めるための職場環境改善のきっかけ”を作るツールです。
WPL診断
これは簡単に言うと、職場の学習環境レベルがどれくらいあるかを診断するツールです。
環境といっても、物理的なものだけでなく、人間関係やルールといった目に見えないものも含まれます。
そして、こういったものの現状を診断し、様々な切り口から職場の学習環境レベルを向上していくということが目的となります。
次回からは、この診断の裏付けとなる理論や事例などについてご紹介していこうと思います。
2009年11月15日
自分に厳しい人の強さ
昨日、映画「沈まぬ太陽」を見てきました。
予告どおり、まさに『魂が、震える』作品だと思います。
キャストがベテランの方ばかりだということもあり、随分感情移入してしまいました。
特に、渡辺謙演じる“恩地元”という人物には心を動かされました。
自分に厳しく、ぶれることのない信念を持って生きる。
周りからの風当たりも強く、人一倍厳しい状況に何度も追い込まれますが、
いつまでも頼り続けられる人物とは、こういった人なんだと思います。
それを確信させる物語になっています。
お金に目がくらんだ人、自分の立場を守ることだけに必死な人、人の強さに嫉妬した人、自分の弱さに負けた人・・・
そういった自身の甘えから抜けられない人はどこかでその化けの皮が剥がされる。
人よりも責任のある立場にいる人ならなお更そうだと。
そんな周りのキャストの役柄と照らし合わせて見ることができるから、自分に厳しい人の強さがはっきりと現れる。
そんな作品でした。
予告どおり、まさに『魂が、震える』作品だと思います。
キャストがベテランの方ばかりだということもあり、随分感情移入してしまいました。
特に、渡辺謙演じる“恩地元”という人物には心を動かされました。
自分に厳しく、ぶれることのない信念を持って生きる。
周りからの風当たりも強く、人一倍厳しい状況に何度も追い込まれますが、
いつまでも頼り続けられる人物とは、こういった人なんだと思います。
それを確信させる物語になっています。
お金に目がくらんだ人、自分の立場を守ることだけに必死な人、人の強さに嫉妬した人、自分の弱さに負けた人・・・
そういった自身の甘えから抜けられない人はどこかでその化けの皮が剥がされる。
人よりも責任のある立場にいる人ならなお更そうだと。
そんな周りのキャストの役柄と照らし合わせて見ることができるから、自分に厳しい人の強さがはっきりと現れる。
そんな作品でした。
2009年11月13日
手探りで見つける“強み”と“弱み”
さて、前回の“暗黙のルール”の話の続きです。
まず、これはどこの会社にも、どんな部署にも存在します。
その会社や部署に悪い影響を与えているものもあれば、良い影響を与えているものもあります。
近しい例で言うと、よく自己分析などに使われているジョハリの窓の『盲点の窓』や『未知の窓』がこれにあたるかと思います。
つまり、上記を言い換えることになりますが、これを見つけることは、“弱み”を発見することにもなれば、“強み”を発見することにも繋がるということです。
では、どうやってそれを見つけるのか。
細かいことはここでは記載しませんが、簡単なところだけをお伝えをすると、そこの会社や部署で普段行われている仕事のプロセスなどをひとつずつ聞き出し、それぞれについて『何故そうしているのか』を素人目でしつこく聞き出していくという方法です。こればっかりは手探りです。
見つけることができれば、そのアプローチ方法を考えることはさほど難しくはありません。ただ、そのアプローチ方法を実現させることは非常に困難で、それを実現させるのが弊社の仕事です。
まず、これはどこの会社にも、どんな部署にも存在します。
その会社や部署に悪い影響を与えているものもあれば、良い影響を与えているものもあります。
近しい例で言うと、よく自己分析などに使われているジョハリの窓の『盲点の窓』や『未知の窓』がこれにあたるかと思います。
つまり、上記を言い換えることになりますが、これを見つけることは、“弱み”を発見することにもなれば、“強み”を発見することにも繋がるということです。
では、どうやってそれを見つけるのか。
細かいことはここでは記載しませんが、簡単なところだけをお伝えをすると、そこの会社や部署で普段行われている仕事のプロセスなどをひとつずつ聞き出し、それぞれについて『何故そうしているのか』を素人目でしつこく聞き出していくという方法です。こればっかりは手探りです。
見つけることができれば、そのアプローチ方法を考えることはさほど難しくはありません。ただ、そのアプローチ方法を実現させることは非常に困難で、それを実現させるのが弊社の仕事です。
タグ :教育
2009年11月12日
ルールや環境が及ぼす影響
前回の『ルール』の記事の続きとなりますが、実は私がお客様に研修教育のご提案をする際に、必ず確認させていただくのが、社内のルールです。
前回の記事に投稿したように、『ルール』というのは“多くの人の行動”をコントロールする力があります。
だからこそそれが、組織を前進させる力になることもあれば、組織を停滞させる大きな壁になることもあります。
私が研修教育のご提案の際に社内のルールについて聞かせていただくのは、研修を実施するに至った問題の原因が、社員のスキル不足ではなく、そのスキルを発揮できる環境がない場合があるからです。
この環境が整っていない状況で研修をしても、スキルは身についたがそれを発揮することができないという結果に終わることがあります。これでは研修を実施する意味がありません。
だから、受講者を取り巻くルールや環境から聞き取りをさせてもらいます。
そして、このルールや環境で非常にやっかいなのが、社内で文章化されているものだけがそれにあたるわけではないということです。いわゆる、“暗黙のルール”というものも、ここで言う聞き出しておくべき『ルール』にあたるということです。
次回は、この“暗黙のルール”について少し深堀していきたいと思います。
前回の記事に投稿したように、『ルール』というのは“多くの人の行動”をコントロールする力があります。
だからこそそれが、組織を前進させる力になることもあれば、組織を停滞させる大きな壁になることもあります。
私が研修教育のご提案の際に社内のルールについて聞かせていただくのは、研修を実施するに至った問題の原因が、社員のスキル不足ではなく、そのスキルを発揮できる環境がない場合があるからです。
この環境が整っていない状況で研修をしても、スキルは身についたがそれを発揮することができないという結果に終わることがあります。これでは研修を実施する意味がありません。
だから、受講者を取り巻くルールや環境から聞き取りをさせてもらいます。
そして、このルールや環境で非常にやっかいなのが、社内で文章化されているものだけがそれにあたるわけではないということです。いわゆる、“暗黙のルール”というものも、ここで言う聞き出しておくべき『ルール』にあたるということです。
次回は、この“暗黙のルール”について少し深堀していきたいと思います。
タグ :教育
2009年11月12日
“歩道を安全に歩ける”
自分は、“歩道を安全に歩けるってのはすごいことだな”と思うことがよくあります。
世の中には車が走っている横で人が歩いている場所なんてたくさんあり、運転手のハンドル操作一つで車が歩道に乗り上げたり、歩道を走ったりすることはいくらでもできるわけです。
しかしながら、“車道は車が走る、歩道は歩行者が歩く”という『ルール』と、歩道を車が走った際に人をひいてしまう可能性があることから連想される人としての『モラル』という2つの縛りで、“歩道を安全に歩ける”という常識が出来上がっています。
『ルール』と『モラル』という2つの目に見えない概念で何千、何億という人が動く。
この2つの目に見えない、しかしながら大きな力を持つ概念が最近の自分の関心ごとです。
世の中には車が走っている横で人が歩いている場所なんてたくさんあり、運転手のハンドル操作一つで車が歩道に乗り上げたり、歩道を走ったりすることはいくらでもできるわけです。
しかしながら、“車道は車が走る、歩道は歩行者が歩く”という『ルール』と、歩道を車が走った際に人をひいてしまう可能性があることから連想される人としての『モラル』という2つの縛りで、“歩道を安全に歩ける”という常識が出来上がっています。
『ルール』と『モラル』という2つの目に見えない概念で何千、何億という人が動く。
この2つの目に見えない、しかしながら大きな力を持つ概念が最近の自分の関心ごとです。
Posted by KNブログ at
00:28
│Comments(0)




